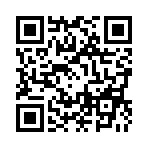2011年05月14日
宅建合格への道
宅建合格には民法が一つの鍵となります。
受験5ケ月前に何をすべきか?
民法を得点現するための基本知識を掲載しています。
今回は、相続人の順位と相続分についてです。
法定相続分については、次のとおり大きく3つの分類になっていることはご存知ですね。
1.配偶者1/2 子1/2
2.配偶者2/3 直系尊属1/3
3.配偶者3/4 兄弟姉妹4/1
ただし、非嫡出子や父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は他の1/2になる。
過去問題集で何度も計算訓練をして覚えていきましょう。
ただし、相続分与の計算については、出題頻度からすると、前回掲載させていただいた
「兄弟姉妹は遺留分がない」擬似計算問題で受験生を惑わせる問題の方が出題される傾向が高いと考えます。
理由については、120分で50問を解く宅建試験に関する時間配分では、計算問題を1問出題がやっとで、計算問題は、他の分野でもっと重要な計算問題があるからです。
私の持論ですが、かなり宅建受験生には浸透しつつあります。
受験5ケ月前に何をすべきか?
民法を得点現するための基本知識を掲載しています。
今回は、相続人の順位と相続分についてです。
法定相続分については、次のとおり大きく3つの分類になっていることはご存知ですね。

1.配偶者1/2 子1/2
2.配偶者2/3 直系尊属1/3
3.配偶者3/4 兄弟姉妹4/1
ただし、非嫡出子や父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹は他の1/2になる。
過去問題集で何度も計算訓練をして覚えていきましょう。
ただし、相続分与の計算については、出題頻度からすると、前回掲載させていただいた
「兄弟姉妹は遺留分がない」擬似計算問題で受験生を惑わせる問題の方が出題される傾向が高いと考えます。
理由については、120分で50問を解く宅建試験に関する時間配分では、計算問題を1問出題がやっとで、計算問題は、他の分野でもっと重要な計算問題があるからです。
私の持論ですが、かなり宅建受験生には浸透しつつあります。

2011年05月13日
地震の影響?
ぐずついた天気で台風1号から変わった低気圧の影響で雨雨雨 ブルーシートを張った屋根では、雨漏りが心配です。
ブルーシートを張った屋根では、雨漏りが心配です。

さて、今回も、宅建民法相続に関する基本問題です〇×て゜回答しましょう。
1.相続人が相続を放棄した場合は、相続開始のときから3ケ月以内に単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければならない。
2.相続開始前の承認、放棄は、認められない。なお、一度、承認、放棄すると、撤回することができない。
回答
1.×本問題の相続開始の起算点については、相続開始を知ったときから3ケ月以内に、単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければならない。
2.〇撤回とは、皆さんは分かっていると思いますが、もう一度確認のために、説明いたします。
撤回は、現時点から将来に向かって事実が有効となるのでしたね。
無効と取消しとのちがいについては、問題を解くうえで、基本知識です。
 ブルーシートを張った屋根では、雨漏りが心配です。
ブルーシートを張った屋根では、雨漏りが心配です。
さて、今回も、宅建民法相続に関する基本問題です〇×て゜回答しましょう。
1.相続人が相続を放棄した場合は、相続開始のときから3ケ月以内に単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければならない。
2.相続開始前の承認、放棄は、認められない。なお、一度、承認、放棄すると、撤回することができない。
回答
1.×本問題の相続開始の起算点については、相続開始を知ったときから3ケ月以内に、単純承認若しくは限定承認又は相続放棄をしなければならない。
2.〇撤回とは、皆さんは分かっていると思いますが、もう一度確認のために、説明いたします。
撤回は、現時点から将来に向かって事実が有効となるのでしたね。
無効と取消しとのちがいについては、問題を解くうえで、基本知識です。
2011年05月13日
宅建民法読解の基本
本日は相続の遺言(いごん)について、基本問題です。
○×で回答してみましょう。
1.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、全部又は一部を撤回することができる。
ただし、撤回権を放棄することはできない。
2.被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人である場合、Aが他人Dに遺産全部を
贈与したとき、Bの遺留分は遺産の3/8、Cの遺留分は遺産の1/8である。
回答
1.○
2.×兄弟姉妹については、遺留分がありません。受験者の頭を計算させるよう仕向け動揺させる問題です。基本知識を持っている皆さんは、
計算しなくても、誤っていることがわかるはずです。
ちなみに(遺留分の割合については、配偶者、子(代襲者含む)直系尊属であり、その割合
については、配偶者、子については、相続財産の1/2、直系尊属については、1/3と
なります。
○×で回答してみましょう。

1.遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、全部又は一部を撤回することができる。
ただし、撤回権を放棄することはできない。
2.被相続人Aの配偶者BとAの弟Cのみが相続人である場合、Aが他人Dに遺産全部を
贈与したとき、Bの遺留分は遺産の3/8、Cの遺留分は遺産の1/8である。
回答
1.○
2.×兄弟姉妹については、遺留分がありません。受験者の頭を計算させるよう仕向け動揺させる問題です。基本知識を持っている皆さんは、
計算しなくても、誤っていることがわかるはずです。
ちなみに(遺留分の割合については、配偶者、子(代襲者含む)直系尊属であり、その割合
については、配偶者、子については、相続財産の1/2、直系尊属については、1/3と
なります。