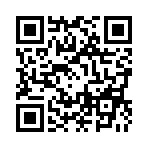2011年06月22日
宅建税金の知識
今回は、不動産に係る法律といたしまして、不動産取得税について、問題です。
なお、課税標準の特例については、平成22年度として掲載しておりますことを予め申し上げます。
〇×で回答してみましょう。
問1不動産取得税の標準主体については4/100であるが、平成22年度中に住宅を取得した場合ら不動産取得税の標準税率は、1.4/100である。
問2床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住に供されたことのないものを、平成22年度4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税については、住宅の価格から1200万円控除される。
回答は下記に掲載いたします。
問1×不動産税率の特例措置については、平成22年度は3/100です。固定資産税との引っ掛け問題です。
似て異なる数字については、受験者を混乱させようと試験問題を作成するときに、好んで゛出題されめ傾向があることに注意をして下さい。
問2×新築住宅を取得した場合に適用される、課税標準の特例の対象となる床面積は、50㎡以上240㎡以下でなければ適用を受けられません。本肢については、33㎡なので特例を受けることができません。


なお、課税標準の特例については、平成22年度として掲載しておりますことを予め申し上げます。
〇×で回答してみましょう。

問1不動産取得税の標準主体については4/100であるが、平成22年度中に住宅を取得した場合ら不動産取得税の標準税率は、1.4/100である。
問2床面積が33㎡である新築された住宅で、まだ人の居住に供されたことのないものを、平成22年度4月に取得した場合、当該取得に係る不動産取得税については、住宅の価格から1200万円控除される。
回答は下記に掲載いたします。
問1×不動産税率の特例措置については、平成22年度は3/100です。固定資産税との引っ掛け問題です。
似て異なる数字については、受験者を混乱させようと試験問題を作成するときに、好んで゛出題されめ傾向があることに注意をして下さい。
問2×新築住宅を取得した場合に適用される、課税標準の特例の対象となる床面積は、50㎡以上240㎡以下でなければ適用を受けられません。本肢については、33㎡なので特例を受けることができません。

2011年06月20日
宅建税金の知識
今回は、不動産に係る税金といたしまして、不動産取得税について、問題です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。
〇×で回答してみましょう。
問1不動産取得税は、不動産の取得に対し、不動産の所在する市町村において、不動産を取得した個人又は法人に課される。なお、徴収方法は、普通徴収方式がとられている。
問2不動産の取得とは、交換・贈与も含まれることから、不動産取得税も適用となる。
問3不動産(土地)を9万円で取得した場合は、不動産取得税が課税されない。
回答は下記に記載します。
問1×不動産取得税の課税主体については、不動産の所在地都道府県が、不動産の取得者へ課税する。
問2○不動産取得税の課税客体は、原始取得(家屋の建築・増改築)のほか承継取得(売買・交換・贈与)も取得原因となります。暗記術といたしましたは、『不動産ゾウをコウ換する』まだ試験に出題されていない重要ポイントです。
問3○免税点については、土地10万円建築23万円その他12万円に満たない場合は、不動産取得税は課税されません。暗記術については、『10(10万)代の兄さん(23万)へ委任(12万)する。』と覚えます。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。

〇×で回答してみましょう。
問1不動産取得税は、不動産の取得に対し、不動産の所在する市町村において、不動産を取得した個人又は法人に課される。なお、徴収方法は、普通徴収方式がとられている。
問2不動産の取得とは、交換・贈与も含まれることから、不動産取得税も適用となる。
問3不動産(土地)を9万円で取得した場合は、不動産取得税が課税されない。
回答は下記に記載します。
問1×不動産取得税の課税主体については、不動産の所在地都道府県が、不動産の取得者へ課税する。
問2○不動産取得税の課税客体は、原始取得(家屋の建築・増改築)のほか承継取得(売買・交換・贈与)も取得原因となります。暗記術といたしましたは、『不動産ゾウをコウ換する』まだ試験に出題されていない重要ポイントです。
問3○免税点については、土地10万円建築23万円その他12万円に満たない場合は、不動産取得税は課税されません。暗記術については、『10(10万)代の兄さん(23万)へ委任(12万)する。』と覚えます。
2011年06月20日
宅建固定資産税
今回は、不動産に係る法律といたしまして、固定資産税について、問題です。
なお、課税標準の特例については、平成22年度として掲載しておりますことを予め申し上げます。
〇×で回答してみましょう。
問1固定資産税の納税義務者については、1月1日現在に所有者として登記、登録している個人又は法人課税される。
問2標準税率については、0.3%である。
問3課税標準の特例については、小規模住宅用地200㎡以下の部分については、6分の1である。
回答は以下のとおりです。
問1○
問2×1.4%暗記方法については、固石(こいし)と覚えておけばいいでしょう。
問3○なお、200㎡を超える部分については、3分の1となりますことを申し添えます。

なお、課税標準の特例については、平成22年度として掲載しておりますことを予め申し上げます。
〇×で回答してみましょう。

問1固定資産税の納税義務者については、1月1日現在に所有者として登記、登録している個人又は法人課税される。
問2標準税率については、0.3%である。
問3課税標準の特例については、小規模住宅用地200㎡以下の部分については、6分の1である。
回答は以下のとおりです。
問1○
問2×1.4%暗記方法については、固石(こいし)と覚えておけばいいでしょう。
問3○なお、200㎡を超える部分については、3分の1となりますことを申し添えます。
2011年06月17日
宅建不動産登記問題と解説
今回は、不動産に係る法律といたしまして、不動産登記について、問題です。
〇×で回答してみましょう。
問1:権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
問2:抵当権の設定の登記は、権利部の乙区に記録される。
問3:登記の申請を共同でしなければならない者の一方に登記をすべきことを命ずる確定判決による登記は、共同でしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
解説は下記のとおり
問1:正しい。権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則。
なお、所有権の保存の登記など、権利に関する登記であっても単独申請が認められるものもある。
問2正しい。
問3正しい。

〇×で回答してみましょう。

問1:権利に関する登記の申請は、原則として、登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならない。
問2:抵当権の設定の登記は、権利部の乙区に記録される。
問3:登記の申請を共同でしなければならない者の一方に登記をすべきことを命ずる確定判決による登記は、共同でしなければならない者の他方が単独で申請することができる。
解説は下記のとおり
問1:正しい。権利に関する登記は、登記権利者と登記義務者が共同して申請するのが原則。
なお、所有権の保存の登記など、権利に関する登記であっても単独申請が認められるものもある。
問2正しい。
問3正しい。
2011年06月14日
宅建登記の知識
今回は、不動産に係る税金といたしまして、登録免許税について、問題です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。
〇×で回答してみましょう。
問1:登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
問2:不動産の表示に関する登記は、登記記録の表題部に、権利に関する登記は、全て権利部甲区に記録される。
回答は以下に掲載します。
回答
1 ○ 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成される。
2 × 表示に関する登記は表題部に、権利に関する登記は権利部にされる。そして権利部にされる登記のうち、所有権の保存の登記など、権利に関する事項は、甲区に、所有権以外の権利に関する登記は、乙区に記録される。

先日、山登りをしてきました、沢には、「サワガニ」がいる噂ですが、水がなくカラカラ状態です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。

〇×で回答してみましょう。
問1:登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成する。
問2:不動産の表示に関する登記は、登記記録の表題部に、権利に関する登記は、全て権利部甲区に記録される。
回答は以下に掲載します。
回答
1 ○ 登記記録は、表題部及び権利部に区分して作成される。
2 × 表示に関する登記は表題部に、権利に関する登記は権利部にされる。そして権利部にされる登記のうち、所有権の保存の登記など、権利に関する事項は、甲区に、所有権以外の権利に関する登記は、乙区に記録される。

先日、山登りをしてきました、沢には、「サワガニ」がいる噂ですが、水がなくカラカラ状態です。
2011年06月13日
税金の知識
今回は、不動産に係る税金といたしまして、登録免許税について、問題です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。
〇×で回答してみましょう。
問1:住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記に対しては、適用されない。
問2:個人が受ける所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、住宅用家屋の取得後1年を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。
問3:個人が受ける所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、床面積が50㎡未満又は240㎡を超える住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。
回答は下記へ記載いたします
回答
問1 誤り。このような制限はない。
問2 正しい。住宅の取得後 1年以内に登記を行う場合であれば、登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
問3 誤り。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅とは、その床面積が50㎡以上のものでなければならないが、床面積に上限はない。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。

〇×で回答してみましょう。
問1:住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置は、既にこの税率の軽減措置の適用を受けたことのある者が受ける登記に対しては、適用されない。
問2:個人が受ける所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、住宅用家屋の取得後1年を経過した後に受ける登記に対しては、適用されない。
問3:個人が受ける所有権移転登記に係る登録免許税の軽減措置の適用を受ける場合、床面積が50㎡未満又は240㎡を超える住宅用家屋の登記に対しては、適用されない。
回答は下記へ記載いたします
回答
問1 誤り。このような制限はない。
問2 正しい。住宅の取得後 1年以内に登記を行う場合であれば、登録免許税の税率の軽減措置の適用を受けることができる。
問3 誤り。住宅用家屋の所有権移転登記に係る登録免許税の税率の軽減措置の対象となる住宅とは、その床面積が50㎡以上のものでなければならないが、床面積に上限はない。
2011年06月12日
税金の知識
今回は、不動産に係る税金といたしまして、登録免許税について、問題です。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。
〇×で回答してみましょう。
問1:売買における所有権移転登記にかかる登録免許税は、原則として登記権利者と登記義務者が連帯納付義務を負う。
問2:登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が千円に満たないときは、その課税標準は千円とする。
回答は以下のとおりです。
解答
1 正しい。記述のとおりである。
2 正しい。記述のとおりである。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。

〇×で回答してみましょう。
問1:売買における所有権移転登記にかかる登録免許税は、原則として登記権利者と登記義務者が連帯納付義務を負う。
問2:登録免許税の課税標準の金額を計算する場合において、その金額が千円に満たないときは、その課税標準は千円とする。
回答は以下のとおりです。
解答
1 正しい。記述のとおりである。
2 正しい。記述のとおりである。
2011年06月09日
税金の知識
今回は、不動産に係る税金といたしまして、登録免許税について、まとめております。
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。
住宅に関わる諸費用のまとめ
1. 登録免許税
表-1
登録免許税
課税主体 国
納税義務者 登記を受ける者共同作成(2人以上)は連帯納付義務
課税標準 不動産の価格※1 債権額など
税 率 表-2参照
納税地 登記を受ける登記所の所在地
納税方法 原則 現金
例外 税額が3万円以下の場合、収入印紙による納税も可
※1 不動産の価格とは、固定資産税台帳価格のことをいう。
2. 登録免許税の特例 表-2
登記の種類 課税標準 税率 住宅の軽減税率適用※1
住宅家屋の所有権保存登記 不動産の価格 1000分の4 1000分の1.5に軽減
住宅家屋所有権移転登記 売買 不動産の価格 1000分の20 1000分の3に軽減
所有権移転登記 相続・合併 不動産の価格 1000分の4
住宅資金貸し付け抵当権設定 債権額 1000分の4 1000分の1軽減
所有権移転仮登記 不動産の価格 1000分の10※2
権利の変更・抹消登記 不動産の個数 1000円
※1 住宅の軽減税率の適用を受ける用件については、次のとおり。
(適応期間平成23年3/31まで)
①個人が受ける登記であること。
②床面積が50㎡以上であること。
③新築又は取得後1年以内の登記であること。
④中古住宅にあっては、上記の他、築年数20年以内、または、一定の耐震基準などに適合するものであること。
※2 所有権移転仮登記を本登記にする場合は、本来の1000分の20から1000分の10を控除
※3 課税標準及び税率が1000円に満たない
なお、軽減税率の適用などについては、毎年変わっていくことから、H22年度の内容で掲載していることを予め申し添えます。

住宅に関わる諸費用のまとめ
1. 登録免許税
表-1
登録免許税
課税主体 国
納税義務者 登記を受ける者共同作成(2人以上)は連帯納付義務
課税標準 不動産の価格※1 債権額など
税 率 表-2参照
納税地 登記を受ける登記所の所在地
納税方法 原則 現金
例外 税額が3万円以下の場合、収入印紙による納税も可
※1 不動産の価格とは、固定資産税台帳価格のことをいう。
2. 登録免許税の特例 表-2
登記の種類 課税標準 税率 住宅の軽減税率適用※1
住宅家屋の所有権保存登記 不動産の価格 1000分の4 1000分の1.5に軽減
住宅家屋所有権移転登記 売買 不動産の価格 1000分の20 1000分の3に軽減
所有権移転登記 相続・合併 不動産の価格 1000分の4
住宅資金貸し付け抵当権設定 債権額 1000分の4 1000分の1軽減
所有権移転仮登記 不動産の価格 1000分の10※2
権利の変更・抹消登記 不動産の個数 1000円
※1 住宅の軽減税率の適用を受ける用件については、次のとおり。
(適応期間平成23年3/31まで)
①個人が受ける登記であること。
②床面積が50㎡以上であること。
③新築又は取得後1年以内の登記であること。
④中古住宅にあっては、上記の他、築年数20年以内、または、一定の耐震基準などに適合するものであること。
※2 所有権移転仮登記を本登記にする場合は、本来の1000分の20から1000分の10を控除
※3 課税標準及び税率が1000円に満たない