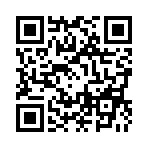2011年06月30日
定期借地するには?
借地借家法は、貸主との関係について、 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて特殊な借地権の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
定期借地権の存続期間については、30年以上となっている。
問2
事業用定期借地権の存続期間については、10年以上30年未満とするときには、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長、買取請求の規定は適用されない。
解説については、以下に掲載します。
問1×
定期借地権の存続期間については、50年以上です。なお、契約の更新がないこと。建物の再築による借地期間の延長がないことの効果があります。暗記術は定年後(後→50年)
問2○
正しい記述。なお、30年以上50年未満にするときは、契約の更新及び建物の築造による存続期間延長がなく、買取請求をしないこととする旨を定めることができます。
 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。では、問題を通じて特殊な借地権の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
定期借地権の存続期間については、30年以上となっている。
問2
事業用定期借地権の存続期間については、10年以上30年未満とするときには、契約の更新及び建物の築造による存続期間の延長、買取請求の規定は適用されない。
解説については、以下に掲載します。
問1×
定期借地権の存続期間については、50年以上です。なお、契約の更新がないこと。建物の再築による借地期間の延長がないことの効果があります。暗記術は定年後(後→50年)

問2○
正しい記述。なお、30年以上50年未満にするときは、契約の更新及び建物の築造による存続期間延長がなく、買取請求をしないこととする旨を定めることができます。
2011年06月29日
宅建特殊な借地権?
借地借家法は、貸主との関係について、 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて特殊な借地権の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
定期借地権については、建物買取請求を有しないなどを公正証書による書面での特約が必要となる。
問2
事業用定期借地権については、事業専用建物の所有を目的として、公正証書により借地権を設定することができる。
解説については、以下に掲載いたします。
問1×
定期借地権については、書面による契約が必要ですが、公正証書に限定していません。
問2○
事業用借地権については、公正証書による契約が必要となります。
問1・問2とも似て異なる(試験作成者は、受験者の頭を混乱させる似て異なるところを出題を好んで出題する傾向があります。)しっかり整理しておくことが必要です。
 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。では、問題を通じて特殊な借地権の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
定期借地権については、建物買取請求を有しないなどを公正証書による書面での特約が必要となる。
問2
事業用定期借地権については、事業専用建物の所有を目的として、公正証書により借地権を設定することができる。
解説については、以下に掲載いたします。
問1×
定期借地権については、書面による契約が必要ですが、公正証書に限定していません。
問2○
事業用借地権については、公正証書による契約が必要となります。
問1・問2とも似て異なる(試験作成者は、受験者の頭を混乱させる似て異なるところを出題を好んで出題する傾向があります。)しっかり整理しておくことが必要です。

2011年06月27日
宅建借地借家法の基礎
借地借家法は、貸主との関係について、 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
A(土地貸借人)が土地を借地して建てた建物を譲渡しようとする場合に、B(借地権設定者)に不利になるおそれのないのに、借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときは、裁判所は、A(土地賃貸人)の申し出により、その承諾に代わる許可をすることができる。
問2
AがB所有の建物を貸借している場合に、Aが第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないのにもかかわらず、Bが承諾をしないときは、裁判所は、Aの申し立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
解説は以下に記載しています。
問1〇
借地の場合、裁判所は、土地の借地をしているA(土地貸借人)の申し出により、承諾に代わる許可をすることができます。
問2×
借家の場合には、裁判所の承諾に代わる許可の制度はない。
問1は借地借家法の借地の問題、問2は借地借家法の借家の問題です。問題文から借地の問題なのか借家の問題なのかを判断できる読解力を必要とする問題です。同じような問題ですが赤文字の文面で〇×比較して考えてみるとスッキリするはずですョ・・・
 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問1
A(土地貸借人)が土地を借地して建てた建物を譲渡しようとする場合に、B(借地権設定者)に不利になるおそれのないのに、借地権設定者が借地権の譲渡の承諾をしないときは、裁判所は、A(土地賃貸人)の申し出により、その承諾に代わる許可をすることができる。
問2
AがB所有の建物を貸借している場合に、Aが第三者に転貸しようとする場合に、その転貸によりBに不利となるおそれがないのにもかかわらず、Bが承諾をしないときは、裁判所は、Aの申し立てにより、Bの承諾に代わる許可を与えることができる。
解説は以下に記載しています。
問1〇
借地の場合、裁判所は、土地の借地をしているA(土地貸借人)の申し出により、承諾に代わる許可をすることができます。
問2×
借家の場合には、裁判所の承諾に代わる許可の制度はない。
問1は借地借家法の借地の問題、問2は借地借家法の借家の問題です。問題文から借地の問題なのか借家の問題なのかを判断できる読解力を必要とする問題です。同じような問題ですが赤文字の文面で〇×比較して考えてみるとスッキリするはずですョ・・・

2011年06月26日
借地や借家するためには?
借地借家法は、貸主との関係について、 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。
では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問題1
存続期間満了時に建物が存在しており、B(貸借人)が更新したい旨の請求をしたときA(貸主)が異議に正当な理由がないときは、契約は、更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
解説は以下に掲載しています。
解説
回答1×
民法では、賃貸借に係る存続期間は原則最長20年と定められています。
借地借家法では、最長の制限はなく、最短で30年と定められています。
なお、今回の問題は、更新の場合についての問題ですので、1回目の更新期間は20年です。
 貸借人の保護を重要視していることで知られています。
貸借人の保護を重要視していることで知られています。では、問題を通じて借地の基礎知識をまとめていきたいと思います。
問題1
存続期間満了時に建物が存在しており、B(貸借人)が更新したい旨の請求をしたときA(貸主)が異議に正当な理由がないときは、契約は、更新したものとみなされ、更新後の存続期間は30年となる。
解説は以下に掲載しています。
解説
回答1×
民法では、賃貸借に係る存続期間は原則最長20年と定められています。
借地借家法では、最長の制限はなく、最短で30年と定められています。
なお、今回の問題は、更新の場合についての問題ですので、1回目の更新期間は20年です。
2011年06月25日
借地借家
借地借家法については、特別法としての位置付けられております。
宅建試験には、ほぼ毎年出題される重要論点がたくさんあることから、民法と似て異なる点について、出題されることが多く比較する勉強方法が必要となる法律です。
次回から詳しく解説していきたいと思います。
暑くなったり、肌寒くなったり『夏カゼ気味』ですが、がんばります。
宅建試験には、ほぼ毎年出題される重要論点がたくさんあることから、民法と似て異なる点について、出題されることが多く比較する勉強方法が必要となる法律です。

次回から詳しく解説していきたいと思います。
暑くなったり、肌寒くなったり『夏カゼ気味』ですが、がんばります。