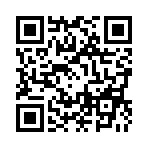2011年05月25日
宅建
前回にひきつづき、不動産物件変動について、掲載いたします。
 さて、不動産物件が変動するケースについて、5つほど掲載いたしましたが、試験で重要とされる登記がなければ第三者に対抗することができない。次の3つの◇◇◇後の第三者がとても重要です。
さて、不動産物件が変動するケースについて、5つほど掲載いたしましたが、試験で重要とされる登記がなければ第三者に対抗することができない。次の3つの◇◇◇後の第三者がとても重要です。
1.取消し後の第三者
2.解除後の第三者
3.時効完成後の第三者
例として、取り消し後の第三者の図を書くと次のような形になりますので頭でイメージしやすくなります。
1.取消し後の第三者
A ⇒ B
①取消し ↓②売却
C
①②の順番で①取り消し→②売却と進んでいることが問題の中から読解できれば難問を解くことができるようになります。
取消し後の第三者に係る問題を○×で回答してみましょう。
問題1.Aが甲地売買契約に係るAB間の契約を取り消した後、BがCへ売却した。所有権移転登記については、Cが所有している場合は、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
回答
1.○上の図のとおりの順番で①AB間取消し→②売却と進んでいることが読解できれば難問をクリアーできます。
取消し後の第三者定番の問題です。
 さて、不動産物件が変動するケースについて、5つほど掲載いたしましたが、試験で重要とされる登記がなければ第三者に対抗することができない。次の3つの◇◇◇後の第三者がとても重要です。
さて、不動産物件が変動するケースについて、5つほど掲載いたしましたが、試験で重要とされる登記がなければ第三者に対抗することができない。次の3つの◇◇◇後の第三者がとても重要です。1.取消し後の第三者
2.解除後の第三者
3.時効完成後の第三者
例として、取り消し後の第三者の図を書くと次のような形になりますので頭でイメージしやすくなります。
1.取消し後の第三者
A ⇒ B
①取消し ↓②売却
C
①②の順番で①取り消し→②売却と進んでいることが問題の中から読解できれば難問を解くことができるようになります。
取消し後の第三者に係る問題を○×で回答してみましょう。
問題1.Aが甲地売買契約に係るAB間の契約を取り消した後、BがCへ売却した。所有権移転登記については、Cが所有している場合は、Cは甲地の所有権をAに対抗できる。
回答
1.○上の図のとおりの順番で①AB間取消し→②売却と進んでいることが読解できれば難問をクリアーできます。
取消し後の第三者定番の問題です。
2011年05月24日
宅建
本日は、宅建民法に係る不動産物件変動について、解説したいと思います。
さて、不動産物件変動については、当事者(売主)と買主が2人登場する二重譲渡のケースが試験に出題される可能性が高い問題です。
二重譲渡の場合は、第三者との関係を「対抗関係」とも呼ばれ、原則、先に登記をした方が他方に優先して所有権を取得することができることとなります。
登記がなければ対抗できない者として想定される場合については、以下の5つがありますが、詳細については、後日改めて、解説いたします。
1.二重譲渡における単純悪意者
2.相続人からの物件取得者
3.特定遺贈の受遺者
4.取得後・解除後の第三者
5.時効完成後の第三者

瓦がたくさん落ちています。
通行に支障がでないよう、道路際によせているようですが、公的機関で早く撤去していただければ・・・
さて、不動産物件変動については、当事者(売主)と買主が2人登場する二重譲渡のケースが試験に出題される可能性が高い問題です。
二重譲渡の場合は、第三者との関係を「対抗関係」とも呼ばれ、原則、先に登記をした方が他方に優先して所有権を取得することができることとなります。
登記がなければ対抗できない者として想定される場合については、以下の5つがありますが、詳細については、後日改めて、解説いたします。

1.二重譲渡における単純悪意者
2.相続人からの物件取得者
3.特定遺贈の受遺者
4.取得後・解除後の第三者
5.時効完成後の第三者

瓦がたくさん落ちています。
通行に支障がでないよう、道路際によせているようですが、公的機関で早く撤去していただければ・・・
2011年04月24日
宅建民法読解の基本
今回は、不動産物件変動について、掲載いたします。
不動産については、所有権移転、移転登記など所有者が変わる場合にさまざまな第三者が現れます。
ついては、第三者に対抗できる登記要件を備えていなければなりません。
登記がなければ第三者に対抗できない者
①二重譲渡による単純悪意者
②相続人からの物件取得者
③特定遺贈の受遺者
④取り消し後・解除後の第三者
⑤時効完成後の第三者
特に◯◯後の第三者が重要ですので、問題文の中から読解することが必要となります。

不動産については、所有権移転、移転登記など所有者が変わる場合にさまざまな第三者が現れます。
ついては、第三者に対抗できる登記要件を備えていなければなりません。
登記がなければ第三者に対抗できない者
①二重譲渡による単純悪意者
②相続人からの物件取得者
③特定遺贈の受遺者
④取り消し後・解除後の第三者
⑤時効完成後の第三者
特に◯◯後の第三者が重要ですので、問題文の中から読解することが必要となります。