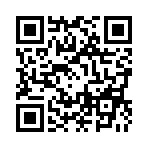2011年07月20日
宅建農地法
宅建に出題される農地法については、たった3条の中から出題されることから、正解率の高い問題です。
とりこぼしのないよう学習しましょう。
次の基本問題を○×で解いてみましょう
問1
農地を一時的に資材置き場に転用する場合は、予め農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項又は第5条1項の許可を受ける必要はない。
問2
市街化区域の農地を耕作の目的に供するため取得する場合は、予め農業委員会へ届出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
解説は以下に掲載いたします。
問1×
農地を資材置き場に転用する場合であっても、原則として農地法第4条又は第5条の許可を受ける必要がある。
ただし、市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会へ届けてれば足りる。
問2×
農地を耕作の目的で取得する場合は、農地が市街化区域内に存在するときでも、農地法第3条の許可を受ける必要がある。
第3条許可の場合は、農業委員会への届出制は存在しません。


とりこぼしのないよう学習しましょう。

次の基本問題を○×で解いてみましょう

問1
農地を一時的に資材置き場に転用する場合は、予め農業委員会へ届出をすれば、農地法第4条第1項又は第5条1項の許可を受ける必要はない。
問2
市街化区域の農地を耕作の目的に供するため取得する場合は、予め農業委員会へ届出れば、農地法第3条第1項の許可を受ける必要はない。
解説は以下に掲載いたします。
問1×
農地を資材置き場に転用する場合であっても、原則として農地法第4条又は第5条の許可を受ける必要がある。
ただし、市街化区域の農地を転用する場合は、農業委員会へ届けてれば足りる。
問2×
農地を耕作の目的で取得する場合は、農地が市街化区域内に存在するときでも、農地法第3条の許可を受ける必要がある。
第3条許可の場合は、農業委員会への届出制は存在しません。


2011年07月16日
宅建暗記術
宅建に出題される農地法については、たった3条の中から出題されることから、正解率の高い問題です。
とりこぼしのないよう学習しましょう。
農地法の概要については、次のとおりです。
3条許可 権利移動
原則 許可権者は農業委員会へ提出
4条許可 転用
原則 許可権者は都道府県知事
例外 転用する農地が4haを超える場合は、農林水産大臣へ提出
5条許可 転用目的の権利移動
原則 許可権者は都道府県知事
例外 取得する農地が4haを超える場合は、農林水産大臣へ提出
3条については、許可権者に農林水産大臣がないことに注意して下さい。
似て異なる部分は、過去問題でもかなり頻繁に出題されていますょ
とりこぼしのないよう学習しましょう。

農地法の概要については、次のとおりです。
3条許可 権利移動
原則 許可権者は農業委員会へ提出
4条許可 転用
原則 許可権者は都道府県知事
例外 転用する農地が4haを超える場合は、農林水産大臣へ提出
5条許可 転用目的の権利移動
原則 許可権者は都道府県知事
例外 取得する農地が4haを超える場合は、農林水産大臣へ提出
3条については、許可権者に農林水産大臣がないことに注意して下さい。
似て異なる部分は、過去問題でもかなり頻繁に出題されていますょ

2011年07月14日
宅建国土利用計画法
前回、掲載させていただきました。国土利用計画法について、問題を通じて覚えていきましょう。 暗記方法をフルに利用して問題を解いてみましょう。
暗記方法をフルに利用して問題を解いてみましょう。
問1
Aが市街化区域について、Bの所有する面積3000㎡の土地を一定の計画に基づいて1500㎡づづ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要ない。
問2
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000㎡の農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件として、DとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
解説は下記へ掲載いたします。
問1×
市街化区域については、2000㎡未満の取引は届出が必要である。
この問題については、個々の土地は2000㎡未満ですが、権利取得者が一定の計画に、合計で3000㎡の一団の土地を取得するので、届出が必要となります。
問2×
届出対象面積については、市街化調整区域は5000㎡以上は届出が必要です。
この問題は、4000㎡なので届出は不要となります。
なお、農地法第5条の許可を停止条件とした契約の場合は、届出が必要とする契約となりますことに注意して下さい。ただし、農地法第3条を受けることを要する場合については、例外として届出不要となることも覚えておきましょう。
 暗記方法をフルに利用して問題を解いてみましょう。
暗記方法をフルに利用して問題を解いてみましょう。
問1
Aが市街化区域について、Bの所有する面積3000㎡の土地を一定の計画に基づいて1500㎡づづ順次購入した場合、Aは事後届出を行う必要ない。
問2
Dが所有する市街化調整区域に所在する面積4000㎡の農地をEに売却する契約を農地法第5条の許可を停止条件として、DとEが締結した場合、Eは事後届出を行う必要がある。
解説は下記へ掲載いたします。
問1×
市街化区域については、2000㎡未満の取引は届出が必要である。
この問題については、個々の土地は2000㎡未満ですが、権利取得者が一定の計画に、合計で3000㎡の一団の土地を取得するので、届出が必要となります。
問2×
届出対象面積については、市街化調整区域は5000㎡以上は届出が必要です。
この問題は、4000㎡なので届出は不要となります。
なお、農地法第5条の許可を停止条件とした契約の場合は、届出が必要とする契約となりますことに注意して下さい。ただし、農地法第3条を受けることを要する場合については、例外として届出不要となることも覚えておきましょう。

2011年07月11日
国土法
宅建に係る法令上の制限で毎年出題される国土利用計画法・・・(°∪°)
ですが、暗記術を利用すればスラスラと覚えられるはずです。 特に、事後の届出については、出題頻度の高い問題です。
特に、事後の届出については、出題頻度の高い問題です。
今回は面積基準について、暗記術です。
市 市街化区域
に 2000㎡未満
長 調整区域・区域区分のない区域
後 5000㎡
万
外 都市計画区域外
準 準都市計画区域 10000㎡
ですが、暗記術を利用すればスラスラと覚えられるはずです。
 特に、事後の届出については、出題頻度の高い問題です。
特に、事後の届出については、出題頻度の高い問題です。今回は面積基準について、暗記術です。
市 市街化区域
に 2000㎡未満
長 調整区域・区域区分のない区域
後 5000㎡
万
外 都市計画区域外
準 準都市計画区域 10000㎡
2011年07月09日
建築基準法
宅建に係る法令上の制限で難問といわれている建築基準法・・・(°∪°)
ですが、暗記術を利用すればスラスラと覚えられるはずです。
1.木造の大規模建築物の暗記方法
階数3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超
参会(3階)する玉をゴメン(5面)と父さん(13)球(9)!!
2.非木造の大規模建築物
階数2階以上、延べ面積200㎡超
2階はメンコ200枚!!
ですが、暗記術を利用すればスラスラと覚えられるはずです。

1.木造の大規模建築物の暗記方法
階数3階以上、延べ面積500㎡超、高さ13m超、軒高9m超
参会(3階)する玉をゴメン(5面)と父さん(13)球(9)!!
2.非木造の大規模建築物
階数2階以上、延べ面積200㎡超
2階はメンコ200枚!!
2011年07月08日
都市計画
宅建試験に係る都市計画法の中で出題傾向の高い、開発進捗度に応じて3種類の制限についてまとめておきましょう。特に次のちがいに注意することです。
比較して覚えてうくと便利ですよ。
1.施工区域内の制限
・建築物の建築については、知事の許可が必要。
例外→管理行為や軽易な行為・非常災害のため必要な応急措置・都市計画事業の施工としてま行為
2.予定区域内の制限
・建築物の建築・工作物の建設・土地の形質の変更(3種類)については、知事の許可が必要。
例外→管理行為や軽易な行為・非常災害のため必要な応急措置・都市計画事業の施工としてま行為
3.事業地内の制限
・建築物の建築・工作物の建設・土地の形質の変更・重量物の設置等(4種類)については、知事の許可が必要。
例外なし
1→2→3と進捗度が増すにつれて、制限の種類が増えていくイメージで覚えることが重要です。
比較して覚えてうくと便利ですよ。

1.施工区域内の制限
・建築物の建築については、知事の許可が必要。
例外→管理行為や軽易な行為・非常災害のため必要な応急措置・都市計画事業の施工としてま行為
2.予定区域内の制限
・建築物の建築・工作物の建設・土地の形質の変更(3種類)については、知事の許可が必要。
例外→管理行為や軽易な行為・非常災害のため必要な応急措置・都市計画事業の施工としてま行為
3.事業地内の制限
・建築物の建築・工作物の建設・土地の形質の変更・重量物の設置等(4種類)については、知事の許可が必要。
例外なし
1→2→3と進捗度が増すにつれて、制限の種類が増えていくイメージで覚えることが重要です。

2011年07月07日
開発行為
都市計画法では、一定規模以上の開発行為をする場合については、知事の許可を必要とします。
問題を通じて覚えていきましょう。
問1
準都市計画区域において、都市計画事業の施工にあたる民間事業者が行う3000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は必要である。
問2
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業にあたらない民間事業者が行う5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。
解説は以下に掲載しています。
問1
準都市計画区域内においては、原則として、3000㎡以上の開発行為を行う場合については、開発許可が必要となります。
ただし、例外として、都市計画事業として行う開発行為については、許可不要となっています。
問2
都市計画区域及び準とし計画区域外については、1ha(10000㎡)以上の開発行為をする場合は、開発許可が必要となるので、5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、許可不要となります。
開発許可に係る数値ものは、出題頻度がかなり高いので、私は次の暗記方法でクリアーしました。
セ→1000㎡ 市街化区域
ミ→未満
の耳→3000未満
準→区域区分のない未線引き地域・準都市計画区域
は意→10000㎡ その他の区域
味→未満
な
い
問題を通じて覚えていきましょう。
問1
準都市計画区域において、都市計画事業の施工にあたる民間事業者が行う3000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、常に開発許可は必要である。
問2
都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、都市計画事業にあたらない民間事業者が行う5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、開発許可は必要である。
解説は以下に掲載しています。
問1
準都市計画区域内においては、原則として、3000㎡以上の開発行為を行う場合については、開発許可が必要となります。
ただし、例外として、都市計画事業として行う開発行為については、許可不要となっています。
問2
都市計画区域及び準とし計画区域外については、1ha(10000㎡)以上の開発行為をする場合は、開発許可が必要となるので、5000㎡の住宅団地建設のための開発行為であれば、許可不要となります。
開発許可に係る数値ものは、出題頻度がかなり高いので、私は次の暗記方法でクリアーしました。
セ→1000㎡ 市街化区域
ミ→未満
の耳→3000未満
準→区域区分のない未線引き地域・準都市計画区域
は意→10000㎡ その他の区域
味→未満
な
い
2011年07月05日
宅建法令制限
宅建試験では、民法が得意でも法令上の制限を不得意とする人がたくさんおります。
民法、法令上の制限、宅建業法、税その他でバランス良く得点できる方が合格できるはずです。
今回は、たくさんの法令から、都市計画法について、掲載いたします。
1区域区分
市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域で概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
市街化調整区域とは、市街化を制御する区域です。
2用途地域
用途地域については、住居系か7種類、商業系他が5種類全部で12種類で構成されいます。
出題分野については、定義がとても重要でそれぞれ次のとおりとなっています。
赤文字のところで用途地域を判断できる記憶力が必要となります。


①第一種低層住専 低層住宅にかかる
②第二種低層住専 主として低層住宅に係る
③第一種中高層住専 中高層住宅に係る
④第二種中高層住専 主として中高層住宅に係る
⑤第一種住居地域 住居の環境を・・・
⑥第二種住居地域 主として住居の環境を・・・
⑦準住居地域 道路の沿道としての・・
⑧近隣商業地域 近隣の住宅地の・・・
⑨商業地域 主として商業・・・
⑩準工業地域 主として環境の悪化を・・・
⑪工業地域 主として工業の利便を・・・
⑫工業専用地域 工業の利便を・・・
民法、法令上の制限、宅建業法、税その他でバランス良く得点できる方が合格できるはずです。
今回は、たくさんの法令から、都市計画法について、掲載いたします。

1区域区分
市街化区域とは、すでに市街化を形成している区域で概ね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図る区域です。
市街化調整区域とは、市街化を制御する区域です。
2用途地域
用途地域については、住居系か7種類、商業系他が5種類全部で12種類で構成されいます。
出題分野については、定義がとても重要でそれぞれ次のとおりとなっています。
赤文字のところで用途地域を判断できる記憶力が必要となります。



①第一種低層住専 低層住宅にかかる
②第二種低層住専 主として低層住宅に係る
③第一種中高層住専 中高層住宅に係る
④第二種中高層住専 主として中高層住宅に係る
⑤第一種住居地域 住居の環境を・・・
⑥第二種住居地域 主として住居の環境を・・・
⑦準住居地域 道路の沿道としての・・
⑧近隣商業地域 近隣の住宅地の・・・
⑨商業地域 主として商業・・・
⑩準工業地域 主として環境の悪化を・・・
⑪工業地域 主として工業の利便を・・・
⑫工業専用地域 工業の利便を・・・